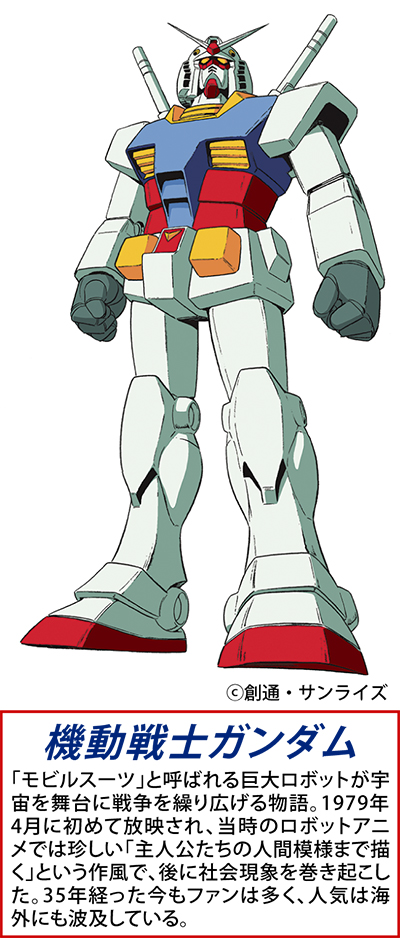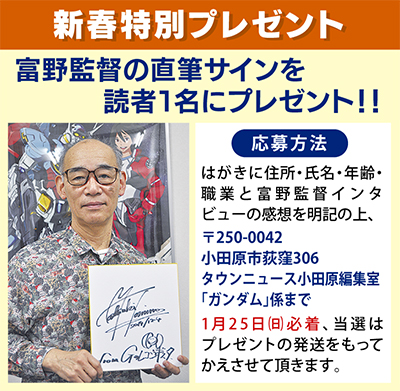New Year Special Interview Gundam the Origin, other. [Japanese Ver.]
New Year Special Interview Gundam the Origin, other. [Japanese Ver.]
新春特別インタビュー ガンダムの原点は小田原!?
[bing_translator]
小田原出身のアニメ原作者・監督である富野由悠季さん(73)が生み出した『機動戦士ガンダム』が35周年を迎えた。現在放映中の記念作品『ガンダム Gのレコンギスタ(以下、G‒レコ)』を製作する東京都杉並区にある(株)サンライズのスタジオを直撃し、これまでの作品に込めた思いと、”リアルな空想”にふけった少年時代について話を聞いた。
中1で想い描いた幻の「小田原空港」
富野監督の少年時代は酒匂川で遊び、絵空事を思い描く日々だった。「小田原と言えば酒匂川」というほど想いは強く、河原の玉砂利の上を裸足で駆け回り、泳ぎを覚えた。
当時は勉強よりも空想が大好きで、教科書を開くと絵空事のアレコレが思い浮ぶ子どもだった。描くのが好きだった飛行機の図面は、「今ある設計図を自分ならこうする」「自分が乗るならこんな飛行機がいい」と、日々想いを巡らせていた。
中学1年の頃に描いた「小田原空港」の設計図も、その一つ。小田原の地図と自らの図面を重ね合わせ、滑走路に必要な距離や箱根山との位置関係、風向き、果ては用地買収に至るまで構想を尽くした。その結果、「小田原に空港は作れない」という結論に至ったというエピソードに、細部にまでこだわる今の監督のルーツを垣間見る。「だから勉強が疎かになっちゃったんだよ」と当時の自分を笑い飛ばした。
そんな富野少年の夢は、東大の航空学科で学び、JAXAのような宇宙関連の仕事でトップを目指すこと。しかし、実際に進学したのは日本大学の芸術学部映像学科。「ここが自分の出発点であり、勉学を怠った結果。当時はこの道に進むしかなかった」と振り返る。今でこそ日本のアニメは世界に誇る地位を確立しているが、当時はまだ「子どもが見るもの」という風潮があったからだ。
卒業後、手塚治虫氏が創設したアニメーション製作会社「虫プロ」に入り、『鉄腕アトム』に携わるなど、着実に経験を積んでいく。アニメで食べていく見込みがついたのは、30代半ばのことだった。
「ガンダムを作った当時、今の自分は全く想像できなかった」と富野監督は話す。自身の代名詞となる『機動戦士ガンダム』を手掛けたのは37歳の時。巨大ロボットブームに乗じて依頼された作品で、「特別作りたいわけではなかった」と当時の心境を明かす。仕事を選り好みしていては、先に進めないという現実。しかし、決して惰性で作品は作らなかった。公共電波に乗せる以上は、テレビの向こう側、視聴者である子どもたちの目を意識しなければ意味がないと、真剣に取り組んだ。
そうして完成したガンダムを、監督は「嘘八百のリアリズム」と評する。「宇宙移民やスペースコロニーなんてありえないと思っているし、二足歩行の乗り物なんて不経済極まりない。あんなのに乗ったら船酔いどころじゃないよ。車輪の乗り物が一番便利」と笑う。「リアルロボットもの」という分野を開拓したとされる富野監督の言葉としては意外に聞こえるかもしれないが、アニメだからこそ「現実ではありえない物」を貪欲に盛り込み、ありえない物をもっともらしく描く。これが監督ならではの手法だ。
「これまでずっと、見て損をしないものが作れる自分を意識してきた。僕はテレビの向こう側にいる子どもたちに対して本気で話しかけてきたつもりだし、そうじゃないと記憶に残る作品は作れない」と持論を語る。
「小田原が嫌い」その裏にあった郷土愛
世間では「小田原嫌い」とも言われている富野監督。本人も認めるところだが、それは郷土に対する想いがあればこそ。「小田原は本来、風光明媚で素晴らしいところ。それを活かせない『今の小田原』が嫌いなんだよ」と感情をあらわにする。飯泉に造られた取水堰については、「御幸の浜の海岸線は、酒匂川から流れる土砂で形成されている。それを堰止めてしまったら、50年後には砂浜がなくなってしまう…」と表情を曇らせた。「ガンダムを作る時はまず、世界観を作らなければいけない。それを考える時、小田原は悪い意味でのサンプルになってしまった」と憂う。
一方で「まちづくりに関しては、行政の視点から見れば仕方がないとも思う部分はある」と理解を示す。生活様式の移り変わりや行動範囲の拡大、郊外型大型店舗や近隣市との動線、それに伴う開発と用地取得などを考えれば必ずしも思い通りにいくわけではないと、冷静に分析する。
「こういう考えが出来るようになったのは、ガンダムを作ったからこそだと思う」。ガンダムの監督として大学教授など様々な人たちとの対談などで得た見識、作品を作る上で多方向からの視点が自分の視野を広げてくれたという。
「酒匂川で北条攻めの布陣を再現するイベントをやったらどうだ。『小田原評定』をやってもいいし、全国の大名の旗を掲げるのも壮観だろう。何より『負け戦をイベントに』なんて他にないだろう」と、さすがの発想。「そうしたら僕は豊臣方の総大将をやるよ。ただし、本気で再現するなら、あの取水堰を壊さなきゃダメ。昔はなかったんだから」とニヤリ。地域資源たる酒匂の原風景を取り戻し、これからの時代に合わせた地域活性に力を注いで欲しいという想いが、そこにはある。
『G‒レコ』に込めた想い
ガンダム登場から35年。「当時とは考え方は変わったし、変わらなければならないと思った」と心境を語る。「脱ガンダム」を考え、悩んだ末に生まれたのが新作『G‒レコ』だった。
新作でとにかく意識したのは、子どもの目線。子どもにも見てもらうため、主人公を明るいキャラクターにし、大人には小難しいことをあまり語らせず、ストーリー展開にスピード感を持たせた。
”富野イズム”ともいえる徹底したリアリズムは今作も健在だ。例えば、作中に出てくる「宇宙エレベーター」。実際にある宇宙エレベーター構想を元にしているが、作中ではあえて輸送機関として描いた。「これだけの規模のものを造るなら、交通機関にしなければ採算が取れない」という監督の考えからだ。また、光をバッテリー化した無限エネルギー「フォトンバッテリー」もその一つ。「無限エネルギーがそう簡単に手に入るわけがない。子どもたちが作品を通して気づき、考えてくれたら」と話す。
「引っかかるフックを1つでも2つでも盛り込んでおけば、子どもたちの記憶に残るアニメになる。記憶に残り、この業界に興味を持てば、子どもたちの中から必ず、次の才能が現れるはずだから」。自分の作品が、次の世界全般を牽引する才能につなげるきっかけの一つになればと願う。自らの人生を費やし携わってきたアニメ業界の未来に、思いを馳せ語る眼差しは、テレビの向こう側に向けられていた。
via townnews.co.jp